子どもにプログラミングを学ばせるメリットとは?

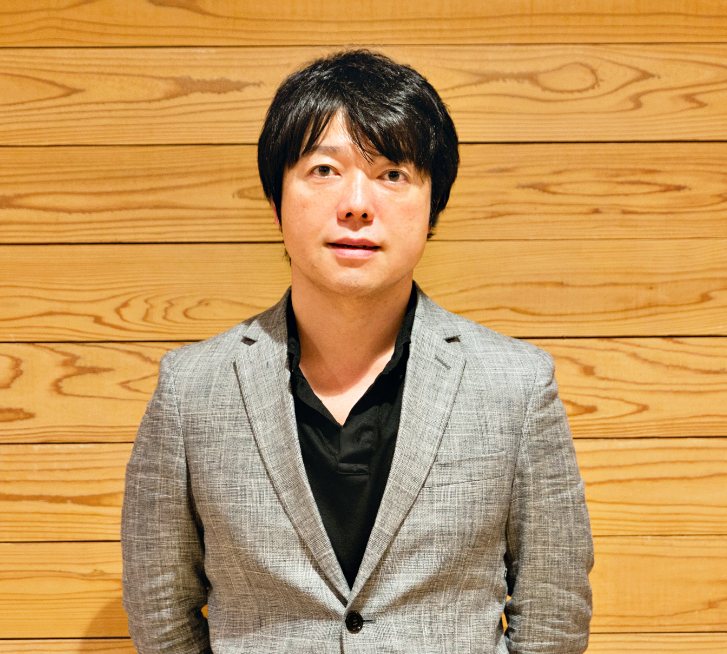
株式会社フロンティアコンサルティング 代表取締役
上岡 正明 (かみおか まさあき)
大学院にてMBA(情報工学博士前期課程)取得。専門分野は社会心理、小児心理。多摩大学、成蹊大学、帝塚山大学で客員講師等を歴任。子どもの脳の発育と行動心理に基づく研究セミナーは常に人気を博している。著者に『死ぬほど読めて忘れない高速読書』(アスコム)、『脳科学者が教える コスパ最強! 勉強法』(ぶんか社)、などベストセラー多数。中国や台湾、韓国でも翻訳され累計85万部となっている。 Twitterフォロアー5万人、YouTubeチャンネル登録者23万人を超える教育系ユーチューバーでもある。
> 監修者の詳細はこちら小学校では、2020年度より「プログラミング」が必修化されるようになりました。
多くの方が誤解していますが、”必修化された”からといって、「プログラミング」という授業が増えるわけではありません。
さまざまな科目を学ぶ上で、新たな学習方法として「プログラミング」が活用されているのです。
つまり、小学校になるまでに「プログラミング」を覚える必要は全く無く、学校でもプログラマーを養成するような内容は行いません。
学習内容については、各市町村や各学校の方針によっても大きく変わりますが、「プログラミングそのものを学ぶ」というよりは「プログラミングを使って論理的な考え方を学ぶ」といった方が近いです。
自分の意図している内容を正確に伝えるには、細かく段階を踏んで、指示を出したり、解説することが重要であることを子どもたちは「プログラミング」を通して学んでいくのです。
今回は、子どもにプログラミングを学ばせるメリットや、何歳から始めれば良いのかといったお悩みに回答していきます。
子どもにプログラミングを学ばせるメリットとは?
普段意識することはあまりありませんが、実は、私たちの生活の中と「プログラミング」は密接な関係にあります。
例えば、毎日使用している家電製品はもちろんのこと、車などの乗り物にもプログラミングは使われています。
子どもたちに身近なところでは、普段よく遊んでいるゲームにもプログラミングが使われていますよね。
プログラミングを学ぶことで、「こんなものがつくれるんだ」ということをまずは、子どもたちに知ってもらうことから始めましょう。
① パソコンの操作に慣れる
今の子どもたちは、学業の中でパソコンをたくさん操作します。
小学校や中学校の授業で使用することも増えますし、もっと大きくなれば、出願などもパソコン上で行うことになるでしょう。
早くからパソコンに触れておけば、苦手意識を持つことなく、パソコンの操作に慣れていきます。
「プログラミング」では、プログラミング言語の使用から、アルファベットや英語といった語学的な勉強も効率よく進めることもでき、一石二鳥です。
② 論理的な考え方を学べる
冒頭でも触れた通り、プログラミングは論理的思考を学ぶことができます。
自分の言いたいこと・やりたいことを相手に伝えるときの方法など、コミュニケーションを行う上でも重要なスキルが身につきます。
③ ルールをつくることができる
プログラミングは、すべて自分でルールを設ける必要があります。
何かゲームを動かすとなると、人は「動かす」ことに夢中になってしまいますが、プログラミングでは「止める」ことも必要になります。
プログラミングをすることで、こういう普段は意識のいかないところまで思考が行き届くので、新しいアイデアが生まれたり、深く考えるクセをつけることができます。
プログラミングは何年生から始めると良い?
プログラミングを始める年齢は何歳でも良いです。
最近では、幼児向け、小学校低学年向けのプログラムもたくさんあるので、早いうちから始めるというのも1つの手です。
ただ、小学校低学年くらいまでは、脳の構造的にプログラムの条件分岐という概念が馴染まないという研究結果もあります。
そういったことを考慮すると、小学校3.4年生くらいから始めても遅くはないといえるでしょう。
まとめ|楽しくプログラミングを学ばせるには?
今は、「アワー・オブ・コード」のようにインターネット上でプログラミング学習ができる時代です。
昔と比べると遥かに勉強しやすく、また、楽しく学べる環境が揃っているといえるでしょう。
また、子どもがやるとなると、親のサポートが必要だと不安になる方もいますが、親がプログラミングスキルを持ち合わせていなくとも子どもの学びはサポートできます。
目に見えて分かりやすい「スクラッチ」といったサイトを使えば、親子で楽しみながらプログラミングを学習できます。
ぜひ、実践してみてください。
