発達障害の子の話し方の特徴4選+コミュニケーションのポイント5選

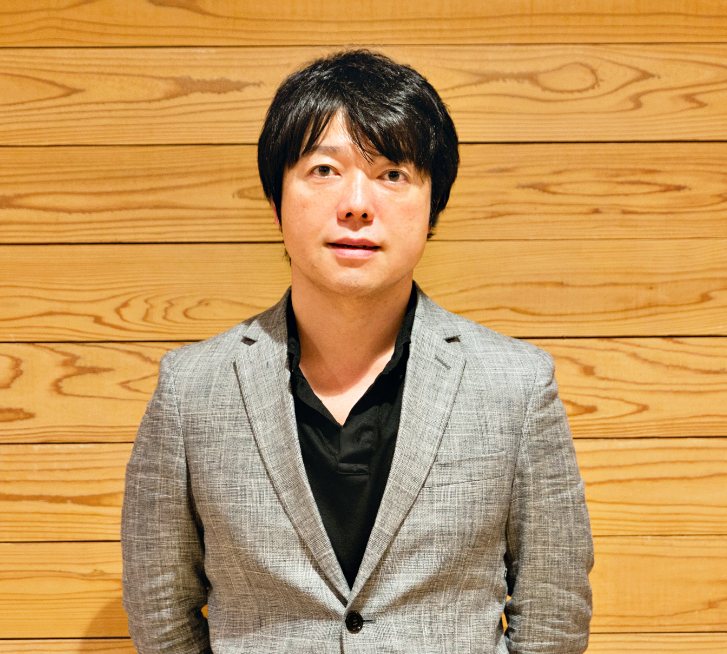
株式会社フロンティアコンサルティング 代表取締役
上岡 正明 (かみおか まさあき)
大学院にてMBA(情報工学博士前期課程)取得。専門分野は社会心理、小児心理。多摩大学、成蹊大学、帝塚山大学で客員講師等を歴任。子どもの脳の発育と行動心理に基づく研究セミナーは常に人気を博している。著者に『死ぬほど読めて忘れない高速読書』(アスコム)、『脳科学者が教える コスパ最強! 勉強法』(ぶんか社)、などベストセラー多数。中国や台湾、韓国でも翻訳され累計85万部となっている。 Twitterフォロアー5万人、YouTubeチャンネル登録者23万人を超える教育系ユーチューバーでもある。
> 監修者の詳細はこちらここでは発達障害のお子さんの話し方の傾向などについて解説していきます。
「話し方や話す内容が特殊で、なかなか理解してあげられない」「子どもともっと楽しくコミュニケーションをしたい」と悩んでいる方は少なくないと思います。
そこで本記事では発達障害のお子さんの話し方の特徴や、お子さんとの楽しく・スムーズにコミュニケーションをするための方法やポイントなどに関してお伝えしていきますので、ぜひ参考にしてください。
発達障害のお子さんの話し方の特徴4選
まずは発達障害のお子さんに多い、話し方の特徴をいくつか紹介していきます。
いずれも発達障害でなくても「話し方が下手」と言われやすい人に出やすい特徴ですが、発達障害のお子さんの場合は特に目立ちます。
1:細かい部分にこだわる
極端に言うと「休みの日って何をしているの?」と聞かれた際に「休みって土曜日?日曜日?」など細かな部分までこだわる人が少なくありません。また、「ゲームが好きだから休みの日はゲームをして、特に最近はマインクラフトが……」など延々説明するような人もいます。
発達障害の方は「相手がどのような情報を求めているか」を察することを苦手とする傾向にあります。しかしそれでも何とか情報を伝えようとして、このようにあらゆる情報を明確にしようとしたり、自分から説明したりする場合があります。
もちろん本人に悪気はありません(他の特徴にも言えることです)。
2:話がまとまらない
話をまとめることを苦手とする傾向にあり、例えば以下のような話し方をする人が少なくありません。
- 同じ内容の話を何度も繰り返す
- 主語が抜ける
- 不要な情報まで盛り込む
- 特定の内容について異様に多く話す
発達障害のお子さんは「どの情報が重要なのかの取捨選択」も上手ではありません。また、感じたこと・思ったことをそのまま口に出す傾向もありますから、話の脈絡がなくなるケースが多いのです。
3:一方的に話す
発達障害のお子さんの中には、相手の表情や反応を見ながら話すことが苦手な人も多いです。そのため相手の様子を見ずに、一方的に話してしまう場合があります。
また、思いつくままに話すという傾向もあるため、相手が話している最中でも、何か考えが浮かぶと遮ってしまうケースが少なくありません。
そして話を遮ることはなくても、「相手が言葉を言い終わる直前」くらいに話し始めて被せてしまうこともあります。
4:相手が知っているか・理解できるかを考慮せずに話す
スムーズに会話するためには「相手がこの内容についてどの程度知っているか・理解しているか」を考慮することも大事ですが、発達障害のお子さんはこれを苦手とする傾向にあります。
例えば親が全く知らないゲームの話をする場合は、「○○というゲームがあって」→「その中に□□というキャラがいて」→「△△という必殺技を使うんだけど」などと話すと理解しやすいです。
しかしいきなり「△△が強くてね!」から話し始めて、相手を困惑させる可能性があります。そして親が「それって何?」と聞き返しても、すでに自分の世界に入ってしまっていて、説明してくれないケースが少なくありません。
発達障害のお子さんの話し方についていくための5つの方法・ポイント
続いて発達障害のお子さんの話し方についていくためのポイントや方法をいくつか紹介していきます。紹介する内容を実践すると、お子さんとのコミュニケーションをより楽しみやすくなりますよ。
1:感情カードを使う
「感情カード」とは文字通り表情のイラストが描かれたカードであり、これを使うことで無表情に近い状態であっても、感情を表に出すことができます。Google画像検索機能を使い「表情カード」などで検索するとヒットします。
カードのイラストが可愛らしく、カードを出す行為そのものも楽しいですから、親子のコミュニケーションが弾みます。感情カードに限らず、親子で共通の「コミュニケーションツール」を使うとやり取りがしやすくなりますからおすすめです。
お子さんに興味があり、親の方に余裕があれば一緒に自作してみるのもいいでしょう。
2:伝えたい内容を紙に箇条書きさせる
「日曜日の午前10時から○○くんと遊びたい」「少し遠い□□公園で遊ぶ」「だから車で送ってほしい」という内容を伝えたいとします。発達障害の場合は話がまとまらず、○○くんの説明に終始したり、なかなか「いつ遊ぶか」を言わなかったりするかもしれません。
しかし伝えた内容を紙に箇条書きすると、発達障害でも話をまとめやすくなります。箇条書きには「文章のつなぎを考えなくていい」「ここまで何を話したかが自分で理解しやすい」「要点を逃しにくい」などのメリットがあるためです。箇条書きの例を挙げます。
- ○○くんと遊びたい
- 日曜日の午前10時から
- 少し遠い□□公園で遊ぶ
- 車で送ってほしい
3:イラストや図を使わせる
イラストや図を使うことで、話の内容がさらにわかりやすく・楽しくなるかもしれません。例えば車に送ってほしい場合は車の絵を描く、○○君と遊びたいなら棒人間を一人描くなどです。
「わかりやすさ」にはつながらない可能性もありますが、コミュニケーションが楽しくなれば、お子さん側が「伝えるのが大変で楽しくないからもう嫌だ!」という状態になりにくくなります。
また、イラストや図と言ってもごく簡単なもので構いません。例えば車も「長方形+丸いタイヤ2つ」などでOKです。「どうせならもっと上手に描こうよ」などと言ってしまうのは絶対にNGですので気を付けてください。
4:親もこれらのツール・方法を積極的に使う
親が感情カード、箇条書き、イラストや図などを積極的に使うからこそ、お子さんが真似したくなります。現状、親→子の方向性の「言葉だけでの伝達」に問題がないとしても、それ以外のコミュニケーションツール・方法をどんどん使っていくことをおすすめします。
5:「伝わらないこと」も含めてお子さんとのコミュニケーションを楽しむ
お子さんとのコミュニケーションを楽しむことが大事です。お子さんとのやり取りに苦労していると徐々にコミュニケーションを、「お子さんの意図・気持ち・考えなどを理解する作業」と捉えるようになるかもしれませんが、本来コミュニケーションは楽しいものです。
それに緊急時や「勉強としてのコミュニケーション練習」などのとき以外は、お子さんの話をすんなり理解できなくても構いませんし、こちらの話がすぐに伝わらなくてもそれほど困らないはずです。
理想的なのは「伝わらないこと」も含めてお子さんとのコミュニケーションを満喫することなのではないでしょうか。難しいかもしれませんが、なかなか伝わらないという現象に対しても「え~、何のことだろう?」「あ、そのことね!」などと笑い合えるといいですね。
まとめ
発達障害のお子さんの話し方は比較的特殊なものになりやすく、親などがお子さんの話の内容を理解することに苦労するケースが少なくありません。ですが箇条書きや感情カードなどを使うことで、コミュニケーションがしやすくなることでしょう。
また、「伝わらないこと」も含めて本来コミュニケーションは楽しいものです。なかなか伝わらない場合も、「これはこれで面白いね」と、親の方から笑うことを意識してみてはいかがでしょうか。
