発達障害の子の感情・感性と付き合うコツ4選

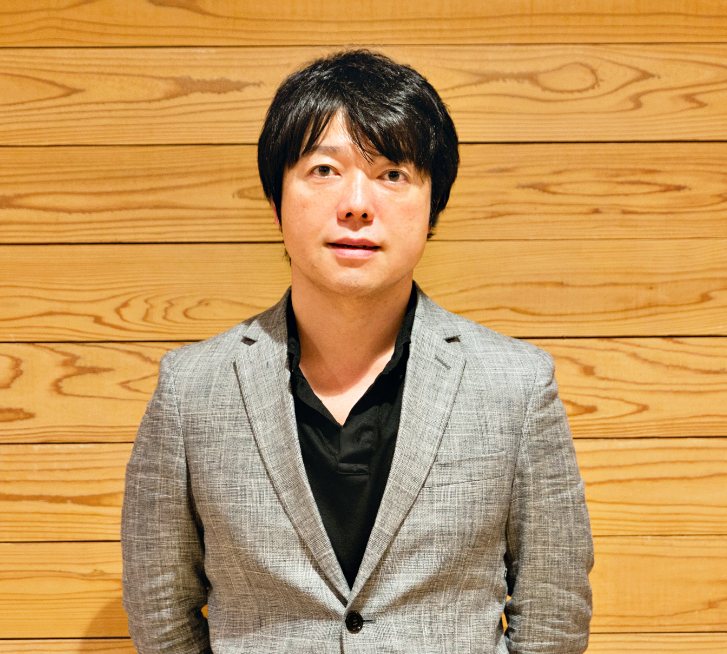
株式会社フロンティアコンサルティング 代表取締役
上岡 正明 (かみおか まさあき)
大学院にてMBA(情報工学博士前期課程)取得。専門分野は社会心理、小児心理。多摩大学、成蹊大学、帝塚山大学で客員講師等を歴任。子どもの脳の発育と行動心理に基づく研究セミナーは常に人気を博している。著者に『死ぬほど読めて忘れない高速読書』(アスコム)、『脳科学者が教える コスパ最強! 勉強法』(ぶんか社)、などベストセラー多数。中国や台湾、韓国でも翻訳され累計85万部となっている。 Twitterフォロアー5万人、YouTubeチャンネル登録者23万人を超える教育系ユーチューバーでもある。
> 監修者の詳細はこちらこの記事では発達障害のお子さんの感情や感性と付き合う方法や考え方などについて解説していきます。
「表情・感情や反応が薄くて親としては少し心配」「感性が独特すぎて、この先いろいろな場面でうまくやっていけるのだろうか」と悩んでいる方は少なくないと思います。
そこで本記事では、発達障害のお子さんの感情や感性の傾向や、それらと上手に付き合う方法などに関してお伝えしていきますので、ぜひ参考にしてください。
発達障害のお子さんの感情・感性の傾向2つ
まずは発達障害のお子さんの感情・感性の傾向を2つ紹介します。あくまで傾向ですが、把握しておくとお子さんとのコミュニケーションなどがしやすくなります。
1:喜怒哀楽が薄い・感情がわかりにくい
「本人が何も思っていない」というわけではないのですが、周りから見ると喜怒哀楽がわかりにくい傾向にあります。そのため周囲とのコミュニケーションに難しさを感じる場合が多いです。
2:感性や物事の捉え方がユニーク
感性や物事の捉え方がユニークであり、周囲から「変わり者」と思われやすいです。
それによって周りから「面白い人」と捉えられればいいのですが、環境・状況によっては「ふざけている」「目立とうとしている」などと認識され、責められて、本人が自信を失っていく場合もあります。
発達障害のお子さんの独特な感情・感性と上手に付き合うための4つのポイント
それでは発達障害のお子さんの感情や感性とうまく付き合っていくためのポイントをいくつか挙げていきます。親の接し方次第で、お子さんのユニークさは「魅力」になりやすいです。
1:表に出さなくてもお子さんの中には「広い世界」があると理解する
発達障害のお子さんを見ていると無表情・無機質に思えるかもしれません。ですがそういったお子さんであっても内面には「広い世界」があって、いろいろなことを思っているはずです。
あなたとしても、頭の中で思っていること・感じていることを何でも表に出すわけではないと思いますが、それと同じです。特に発達障害の場合は、頭の中で激しく思考や衝動が切り替わる人も少なくないため、むしろ親よりも広大な世界を持っているかもしれません。
そのため例えば一緒に公園に出掛けた際にぼーっとしているお子さんの様子を見たら、「表情や態度に出ていないだけで楽しんでいるのかもしれない」と考えてみましょう。お子さんがどのようなことを感じているのか想像してみるのも面白いですよ。
2:お子さん独自の感覚・世界観を否定しない
「満開の花」はキレイで、「枯れた花」には魅力を感じない人が多いです。学校教育などでもこれを「一般的な感性」として教えるかもしれません。「こう感じない人はおかしいです」ではなく「こう感じる人が多いです」と伝えるだけなら、必要な教育と言えるでしょう。
しかし、お子さんが「枯れた花の方が好き」と語るのであれば、その感性を否定してはいけません。本人にとっては純然たる事実であり、それを「おかしい」「変だ」と否定されるのは非常に辛いことだからです。
ですが、子どもは良くも悪くも純粋ですからクラスメイトなどに「○○くん・さんは変だよ」と言われることも多くなることでしょう。だからこそ親だけは、お子さんの理解者でいることが大事です。
3:絵の具、楽器、パソコンなどその子に合った表現手段を与えてみる
絵の具、楽器、パソコンなど、その子自身が興味を持っている表現手段を与えてみると、すさまじい勢いで「自分の世界」を外側に広げていくかもしれません。
そして、それに対して反応をもらうことができると自信がつき、「自分はどのように考えたり感じたりしても良い」と自己肯定感を高めやすくなります。また、表現をすることには、情緒を安定させる効果もあるとされています。
もちろんこういった芸術寄りの表現が苦手でも、お喋りなどで自分を表現することもできるはずです。他の大人はついてこれないかもしれませんが、親だけはお子さんのユニークで魅力的な世界を認めて、気軽に楽しんでみてはいかがでしょうか。
4:他人の感情・感性を完璧に理解することはできないと考える
発達障害であってもなくても、他人の感情や感性を完璧に理解することはできません。これは親子間であっても同じことです。また、一人ひとりの感情や感性が原因で、ときに他人とぶつかることがあるのも普通のことです。
ですから「完璧には理解できない」「だからこそできる限り歩み寄っていくことが大事」と考えてみてはいかがでしょうか。
まとめ
発達障害のお子さんは他人から見ると「無表情・無機質」と感じるかもしれませんが、本人の内面には広い世界があります。また、感性が一風変わっているように見えても、それが本人にとっては事実ですから否定してはいけません。
その「一風変わった部分」が本人の個性であり魅力でもあります。絵の具、楽器、パソコンなどの表現手段を与えると、芸術方面でも活躍できるかもしれませんから試してみてはいかがでしょうか。「表に出てくるお子さんの世界」の一部を、親も楽しめると素敵ですね。
