発達障害の共感力の低さをケアするポイント3つ

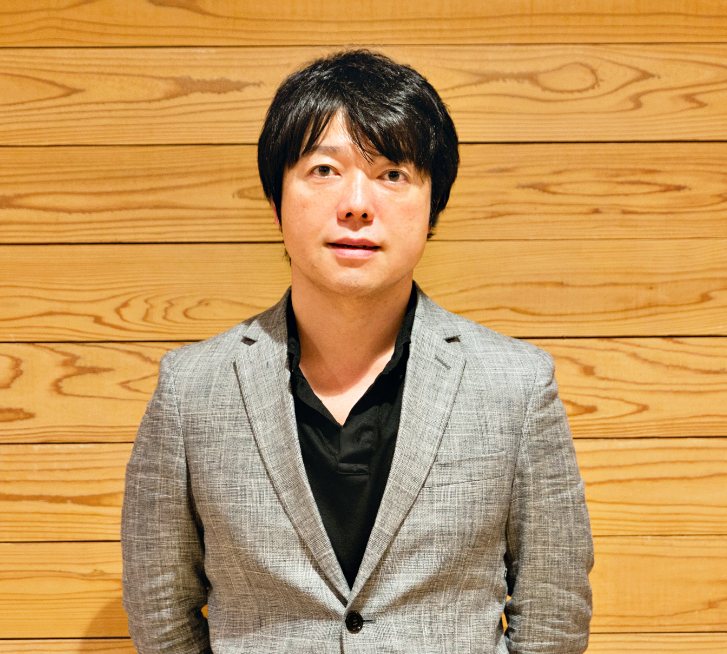
株式会社フロンティアコンサルティング 代表取締役
上岡 正明 (かみおか まさあき)
大学院にてMBA(情報工学博士前期課程)取得。専門分野は社会心理、小児心理。多摩大学、成蹊大学、帝塚山大学で客員講師等を歴任。子どもの脳の発育と行動心理に基づく研究セミナーは常に人気を博している。著者に『死ぬほど読めて忘れない高速読書』(アスコム)、『脳科学者が教える コスパ最強! 勉強法』(ぶんか社)、などベストセラー多数。中国や台湾、韓国でも翻訳され累計85万部となっている。 Twitterフォロアー5万人、YouTubeチャンネル登録者23万人を超える教育系ユーチューバーでもある。
> 監修者の詳細はこちらこの記事では発達障害のお子さんに多い「共感力が低い」という特徴などについて解説していきます。
「空気が読めないようで心配」「他人の気持ちがわからないせいでトラブルを起こしたことがある」などと悩んでいる方は少なくないと思います。
そこで本記事では、「共感力が低い≠優しさがない」という観点について、さらには発達障害のお子さん共感力の低さをケアする方法、共感力が低いことのメリットなどに関してお伝えしていきます。
「空気が読めない・共感力が低い」と「優しさ・思いやりがない」は別|発達障害ケア
発達障害のお子さんは空気が読めなかったり、人の気持ちを理解するのが難しかったりする傾向にあります。最近では「共感力が低い」などと言われることもあります。ですが共感力が低いからといって、優しさや思いやりがないわけではありません。
周りの状況に気付いていなかったり、相手の表情や声色を正確に読み取れていなかったりするだけという場合も多いからです。発達障害でなくても「相手が怒っているなんてわからなかった」と感じるケースはありますが、発達障害だとそれが起きやすいというだけです。
そしてお子さんの周囲が、それほど自分の感情などをわかりやすく表現していないにもかかわらず、「空気を読め」「人の気持ちを理解しろ」と求め過ぎてしまうケースもあります。
発達障害のお子さんの「空気が読めない・共感力が低い」をケアするポイント3選
それでは発達障害のお子さんの空気の読めなさや共感力の低さをケアするためのポイントをいくつか挙げていきますので参考にしてください。あくまで「ケア」ですので、お子さんに現状以上の何かを求めることは基本的にしません。
1:親は感情を言葉などでわかりやすく表現する
空気を読んだり共感力が低かったりするのであれば、親の方からお子さんが理解できるように発信すればいいのです。例えば以下の通りです。
- 表情や声色をわかりやすく作り「ありがとう、嬉しいよ」「それは腹立つよ」などと言う
- 感情を込めて喋りながら、ニコニコマークや怒りマークがついた「表情カード」を見せる
- 一緒にアニメを観ながら「感動した」などと言う
このようにすれば「親は今どんな気持ちなのか」がハッキリわかりますし、慣れてくれば親以外に関しても「今、このような気持ちのはず」などと理解できるようになっていくかもしれません。
2:無言で怒る・無視するなどはNG
学校の先生の中には「明確に叱らず無言で教室を出る」「生徒が謝りにくるまで待つ」という怒り方をする人もいます。これには子どもに何が悪かったのか考えさせる、責任を取らせる(謝りに来させる)などの意味があります。
しかし親が、発達障害のお子さんに対して同じような叱り方をすることはおすすめしません。共感力が低いため「叱られている」と気付かない可能性がありますし、気付いても「なぜ怒られているのか」までは想像できない場合が多いためです。
お子さんとしては「よくわからないがとにかく親に嫌われた」と酷く落ち込むでしょうし、率直に言って時間の無駄です。なので叱るときは「あなたが○○をしたことに対して怒っている」と理由をきちんと伝え、表情も作りましょう。
3:共感できないことを叱らない(他人に完璧に共感できる人はいない)
共感ができていない・人の気持ちを見誤ったお子さんを責めてはいけません。なぜなら他人に完璧に共感できる人はいないからです。これは発達障害であってもなくても同じことです。
例えば親の立場で「お子さんが自分(親)に共感してくれていない」のであれば先ほどお伝えした通り「今、○○な気持ちだよ」と口で説明するべきです。
また、共感できないことで他人を怒らせたり迷惑をかけたりした際には謝ったり、場合によっては「口で何も言ってくれないのに怒られても困ります」と冷静に反論したりすればいいだけです。
発達障害のお子さんの共感力の低いことがもたらす2つのメリット
意外に思えるかもしれませんが、実は発達障害のお子さんの共感力の低いことは、本人や周りにとってメリットになる場合もあります。
もちろん「メリットになるのだから共感する必要はない」と開き直るべきではありませんが、良い部分もありますのでぜひ参考にしてください。
1:相手にとってかえって話しやすい場合もある
特にあまり打ち解けていない人が相手の場合、「あなたの気持ちがよくわかります」という内容の言葉や態度を取ると、「私の何がわかるんだ」「わざとらしい反応はいらないから、話を進めさせてほしい」と思われる可能性もあります。
一方、共感力が低いと、相手の言葉を「そうなんですね」と軽く認めるだけに留まったり、たまに「面白そう」「辛いですね」と自分の感想を言ったりするだけになったりしやすいため、相手にとってかえって話しやすくなる場合が少なくありません。
2:心が疲れにくい
共感力が高い人の中には、例えば「他人の悲しみで過剰に心を傷める」「相手の悲しみと自分の悲しみの区別がつかなくなる」という方もいます。また、「何かしてあげないと」と考え・実行しすぎて疲弊したり、助けられなくて落ち込みすぎたりする人も珍しくありません。
しかし共感力が低いと、こういった理由で自分自身にダメージを与えることは少なくなります。
一見冷たいように思えるかもしれませんが、発達障害の方はただでさえ日常の様々な場面で心身ともに疲れやすいですから、「他人のことでむやみに疲弊しない」というのはバランスが取れているとも言えます。
まとめ
発達障害のお子さんの中には共感力が低い人も少なくありませんが、それは優しさがないというわけではなく、単に周りの状況や他人の感情に気付いてないだけである場合が多いです。
気付けば優しさや思いやりを見せてくれるものですので、それを引き出すためにも親や周りの人が工夫しましょう。また、共感力の低さは本人の強みにもなり得ますから、親の立場でも見習うべき部分があるかもしれません。
