発達障害の子の「空気が読めない」をフォローするための4つのポイント
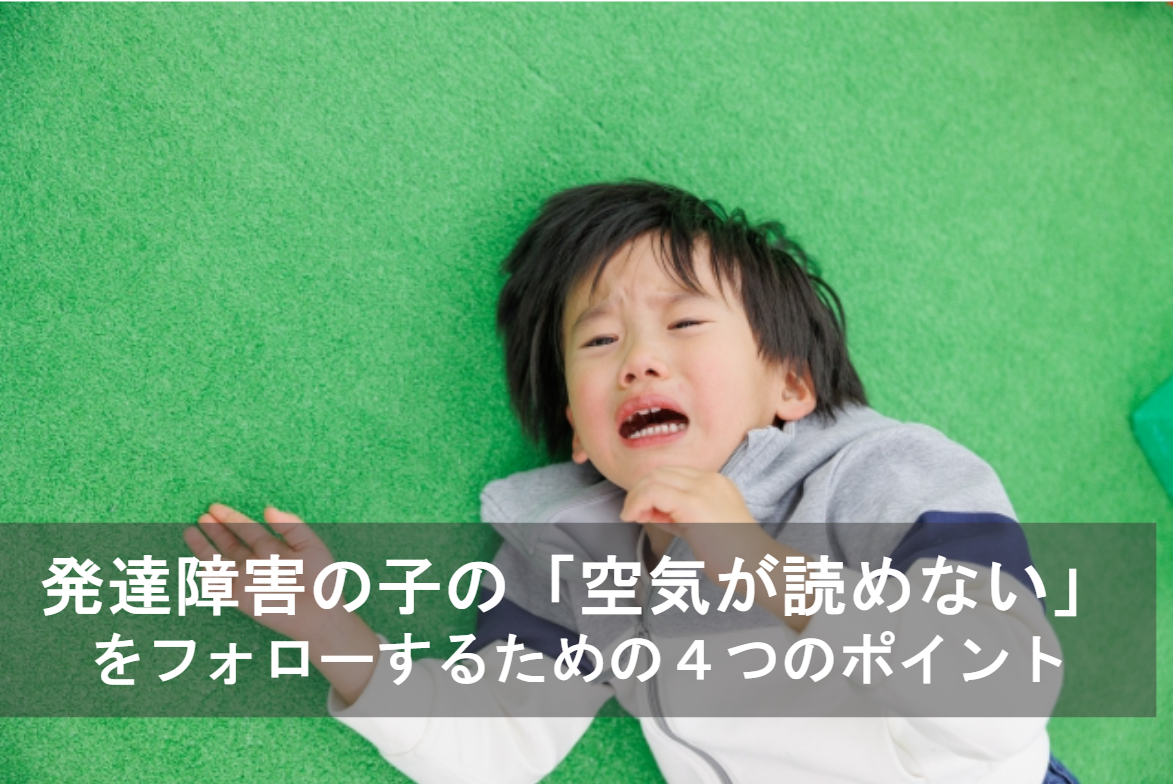
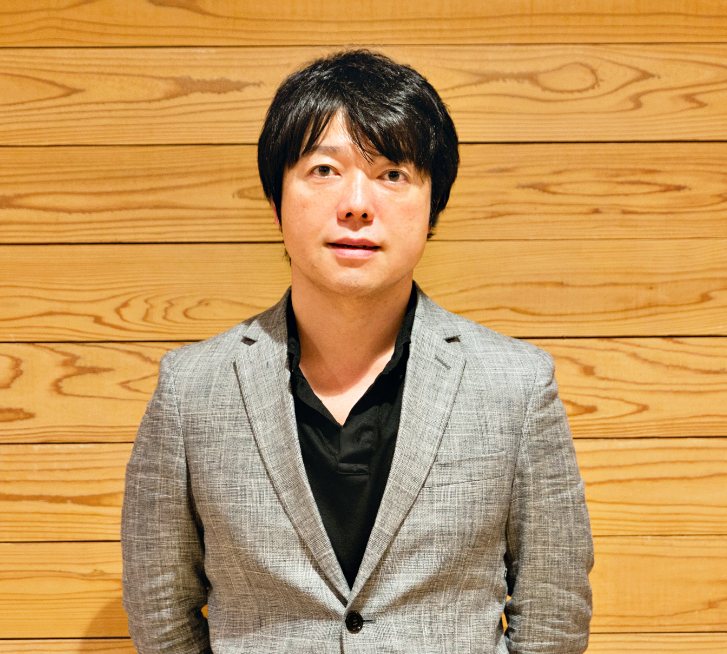
株式会社フロンティアコンサルティング 代表取締役
上岡 正明 (かみおか まさあき)
大学院にてMBA(情報工学博士前期課程)取得。専門分野は社会心理、小児心理。多摩大学、成蹊大学、帝塚山大学で客員講師等を歴任。子どもの脳の発育と行動心理に基づく研究セミナーは常に人気を博している。著者に『死ぬほど読めて忘れない高速読書』(アスコム)、『脳科学者が教える コスパ最強! 勉強法』(ぶんか社)、などベストセラー多数。中国や台湾、韓国でも翻訳され累計85万部となっている。 Twitterフォロアー5万人、YouTubeチャンネル登録者23万人を超える教育系ユーチューバーでもある。
> 監修者の詳細はこちらこの記事では発達障害のお子さんに多い「空気が読めない」をフォローするためのポイントなどについて解説していきます。
「空気が読めないせいで子どもが迷惑をかけたことがある」「どこかのタイミングで爆弾発言をしそうで怖い」と悩んでいる方は少なくないと思います。
そこで本記事では、そもそも空気を読むとは何か、発達障害のお子さんが空気を読めない理由、空気が読めないお子さんをサポートするためのポイントなどに関してお伝えしていきます。
「空気を読むという行為」の4ステップ|発達障害ケア
当然のように使われている「空気を読む」という言葉ですが、実際にはどのような行為のことを指すのでしょうか。4ステップで解説していきます。
お読みいただくと、発達障害であるかないかに関わらず、空気を読むという行為の難易度の高さがわかるはずです。
1:まずは他人の顔色・表情などからいろいろと把握する
まずは他人の顔色、言動、表情、声色、その人の性格、それまでの経緯などいろいろなことを把握します。言わば「自分の次の行動のための判断材料」を集めているようなものです。
2:把握した情報をもとに「その場の状況」を推測する
次に、把握した情報をもとに「その場の状況」を推測します。例えば「お母さんが、今度○○に遊びに行こうねと言っている」「でも言い方からすると、あまり本気ではなさそう」「お母さんは普段から結構テキトーなことを言うし」などです。
3:自分がどう振る舞うべきなのかを考える
推測した内容から自分がどのように行動するべきなのかを考えます。例えば「お母さんは本気で○○に遊びに連れて行ってくれるわけではないはず」「だから自分も『うん、いつかお願いね~』とテキトーに流すべき」などですね。
4:実際にそのように行動する
そして自分で考えたように行動します。ここまで解説している例で言えば、「うん、いつかお願いね~」と軽く返事をすることになります。
「考えたことを実行すればいいだけ」と感じるかもしれませんが、発達障害であってもなくても、「考え」と「行動」が一致しないことは少なくありません。
発達障害の人は空気が読めないと言われやすい4つの理由
続いては発達障害のお子さんが、周囲に「空気が読めない」と言われやすい主な理由を挙げていきます。お子さんの特徴によって理由は変わりますが、いずれの要因も把握しておけばお子さんをサポートしやすくなります。
1:「相手の視点」に立ちにくい
発達障害のお子さんの中には、相手の視点に立って考えることを苦手としている人が少なくありません。そのため「きっとこのような気持ちで話しているはず」「Aと言いつつも、Bを望んでいるのだろな」などと想像することが難しいです。
2:共感能力が低い
発達障害の方は、相手の表情や言動から相手の状況を理解する、相手の行動を見て自分の行動を調整するなどのことを苦手とする傾向にあります。そのため例えば、以下のような行動を取ってしまう場合があります。
- 急いでいる人に対して長い質問をする
- 相手があっけに取られていても、長々と自分のことを話し続ける
- ビジネスマナーなどに沿って行動することができない
3:こだわりが強い・考えが偏りやすい
発達障害の方の中にはこだわりが強く自分の行動をなかなか変化させることができない人や、考え方が偏りやすくて言動も極端になりやすい人などが少なくありません。
このような人の場合、先ほど解説した空気を読む4ステップの「どう振る舞うべきか考える」ことまではできても、実際の行動に反映させられないことが多いです。
つまり「わかっているのにやめられなかった」「した方がいいのにできなかった」という状態ですね。
4:衝動性が強い
発達障害のお子さんの中には衝動性が強い人も多いです。衝動的に行動してしまったり、やめたくてもやめられなくなったりするのです。
「空気を読むこと」をしようとすると、「本来したくはないこと」をすることになる場合が多いです。もしくは「本来したいことをしない」というケースもあるでしょう。つまりは「我慢」が必要なのですが、衝動性が強いとやはり我慢も苦手です。
発達障害の子の空気が読めないことをケアするための4つのポイント
続いては発達障害のお子さんの空気が読めないことに関してケアするためのポイントをいくつか挙げていきます。重要なのは「空気を読めないこと自体はダメではない」ということです。
1:そもそも空気が読めない=ダメではないと理解する
「空気が読めない」という言葉からはマイナスのイメージを抱くでしょう。特に本音と建前の文化が根強い日本人の場合、「空気が読めないこと=短所」と捉えている人が多いと思います。
実際、空気が読めないことによって他人を嫌な思いにさせたり、トラブルを起こしたりする可能性もあります。
ただ、「空気が読めない=ダメ」ではないということも忘れてはいけません。
「空気を読ませようとする側」にも問題がある場合も
例えば、学校の授業で「わかる人は手を挙げて」と先生に言われて、実際に一人だけ手を挙げると「空気が読めない」と言われる場合があります。これは明らかに悪しき風習であり、むしろ手を挙げた子どもの積極性こそが認められるべきです。
また、「言わなくてもわかってほしい」「建前で言っただけなのに本気で受け取るとは……」などもあると思いますが、そういった文化がトラブルの原因になることもあります。理解してほしいことはきちんと口に出すべきという考え方もあるはずです。
もちろん「すべて正直であるのが最適」ということではありませんが、お子さんの「空気が読めない姿」から学べることも多いのではないでしょうか。そして「空気の読めない正直な発言」が誰かを救うこともあるはずです。
2:「感情が素直に表情に出るなら健全」と考える
「悲しいときは悲しい表情になる」「嬉しいときは嬉しい表情になる」などの言動は、場合によっては周囲に空気が読めないと思われることもありますが、「感情が言動に素直に表れるのであれば健全」とも言われています。
そして成長するにつれて我慢も身に付いてきて、「表情に出るだけで具体的な行動は我慢する」「相手が嫌がるのでできるだけ顔に出さない」などの、空気を読む行動もできるようになっていくとされています。
むしろ「気持ち・言葉・行動」が一致していない場面が多い人は、精神的なストレスを溜めていくという見方もあります。何事もバランスではありますが、まずは親が「空気が読めないからこその健全さ」にも目を向けてみてはいかがでしょうか。
3:積極的に他人を関わって自分を理解してもらえるようにサポートする
空気が読めないと言われて雰囲気が悪くなったり、トラブルが起きたりする理由の一つに、相手との関わりが薄いということがあります。逆に相手と相互理解していれば、「少しユニークでも、この人はこういう人だから」と思われて、良い意味で流されるはずです。
そのため積極的に他人と関わって、お子さんが周囲に理解されるように親などがサポートしていくことをおすすめします。
「子どもが迷惑をかけないように……」と考えすぎると消極的になりやすいですが、「人と関わる以上は互いに迷惑をかけ合うもの」「迷惑をかけてしまったら誠実に対応すればいい」と考えるといいでしょう。
4:技術として空気が読めるようにサポートしていく
特に発達障害のお子さんの場合、親などに「もっと空気を読みなさい」と言われても、それが何のことかわかりませんし、わかったとして実現できないはずです。無理矢理空気を読もうとすると委縮して、ストレスを溜めて、何事にも消極的になる恐れがあります。
そのため発想を少し変えて「技術」として空気が読めるようにサポートしていくことをおすすめします。例えば以下の通りです。
- セルフコントロールの技術を教える
- ソーシャルスキルを身に付けさせる
- 行動する前に許可を取る習慣を付けさせる
まとめ
発達障害のお子さんの空気が読めない理由や対策方法などについて解説しましたが、そもそも必ずしも「空気が読めない=ダメ」ではないということを親がきちんと理解しておきましょう。
必要なのは「空気を読むこと」というよりも、「空気が読めなくても周囲と過ごせるように調整していくこと」です。
